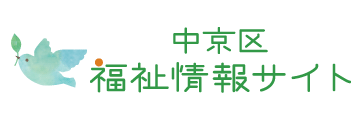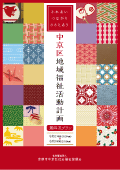中高生の居場所の情報交換会を初めて開催しました!9団体と関係機関5機関が集まって中高生の現状や居場所について情報交換しました。
実施日:7月8日(火)17時~18時半 場所:リブラン京都 LUXE
📌中京区の中高生の居場所
中京区社協より中京区の中高生の居場所にまつわる動向をお知らせ
☑中京区域に子どもの居場所が増加して、6年ほど経過
☑子どもの居場所にこれまで通っていた子どもたちが中高生になる時期
上記2点の背景からここ2年で中高生支援の居場所が同時多発で立ち上がってきました。現在中高生支援の居場所は中央青少年活動センターを含め7か所あります。他にも小学生だけでなく中高生も参加できる居場所もあります。地理的には、中京区東エリアには子どもの居場所の数も中学校数も少ない現状があります。
📌活動紹介
中央青少年活動センターの活動紹介を話題提供とし、それぞれの活動の紹介を行いました。活動日時や活動場所に加えて、自分たちの団体の得意にしていることについて紹介し合い、それぞれの団体に持ち帰った後に子どもたちに紹介し活用できることを大事に行いました。その後は、それぞれの団体が質問する形での意見交換を行いました。意見交換の内容を簡単にレポートします!
📌制度の狭間の取組みですよね?
中高生の居場所事業の資金ってどうしてますか?という質問に対して・・・・
☑共同募金など助成金を活用
☑府からの委託事業費を出せないか交渉
☑カフェ営業のお金を取組にまわす
など、それぞれの工夫が意見交換され、中高生の居場所事業は制度の狭間で支援がほぼない実態を共有しました。
その中で「この事業は、本来は地域のボランタリーではなく社会で光を当て、国の制度として取り組んでいくべきもの。安心して取り組めるようにしていってほしい。」という声もあがっていました。
📌中高生のニーズって学習支援なの?
小学生の支援は、遊びや食事など様々。「中学生になるとぐっと増えるのが『学習支援』どうして??」「中央青少年活動センターも何をしてもいいセンターだが、自習に来る学生も多い!」「子どもたちの主訴も学習になり始める」といったような学習についての意見がでました。
ある団体からは、「中学生なって、算数が数学になって、英語が本格的に増えて、社会が地理や歴史になって、進路学習が始まる。周りの子が塾に行く中で『おっちゃん、僕中学は行って自分ちが貧困って知ったわ。塾いけへん』という子どもからの声を聴いた。」と中学生にとって学習の壁の高さについて示唆されました。
それに対し、別の団体からは、「学習支援も初めはやろうと思ったが、中途半場にやれないと思い辞めた。今はとにかく一歩外に出る居場所として取り組んでいる。元気になってきた子ややる気がわいてきた子には、他の団体の情報を集めて、紹介するようにしている」とのこと。
「子どもたちは子どもなりに『ここはわからないことを教えてもらえる居場所』『ここは遊ぶところ』と選んでいるのかも?」といった意見もあり、そのためには今回のように支援者や居場所の団体がお互いを知り合い紹介しあえる横のネットワーク作りが大切であることを改めて再認識しました。
「学習支援は学習支援が必要と感じた子どもにしか提供できない。学習を必要と自覚できない子はどうなるのか。居場所が必要な子もいるのではないか。」といった問題意識も上がっており、これからの課題についてどう取り組んでいくべきか考える時間となりました。

終わりに、今回会場として使用させていただいたリブラン京都LUXEの建物は町家をリノベーションしたおしゃれな空間。みんなと同じようにカフェで勉強したいという子どもや保護者の思いにこたえることが出来ればという思いから生まれたという。経済的理由や何らかの理由で、同級生の子たちと同じ経験ができない子どももいます。
「小学生の時の課題や困りは中学校で終わらない」
家庭の困りは抱えたまま、発達のしんどさのある子は余計にしんどい、小学校へ行きづらい子は中学校にあがっても1日も登校できない子もいる中で、小学校の時にせっかくつながった子どもの居場所を大事にしていきたい思いを共有しました。委託事業では小学生までという実態や、助成金も小学生を対象とすることも多いです。中高生になっても通える場につなぎなおすこと、子どもの居場所関係者や関係機関が顔の見える関係性をつむいでおくことで、子どもたちを中京区内で取りこぼさない緩やかなネットワークが続いていくようになればと思っております。